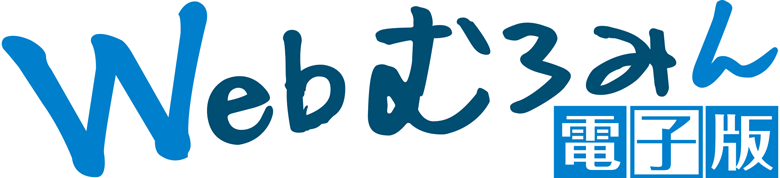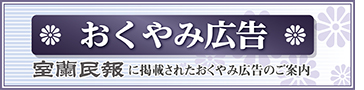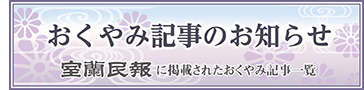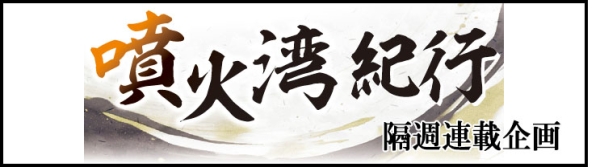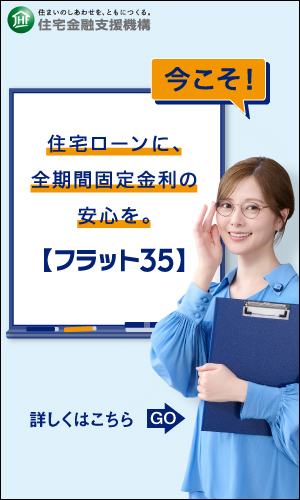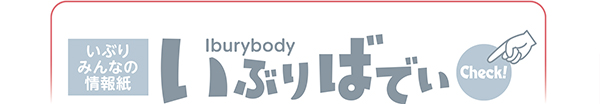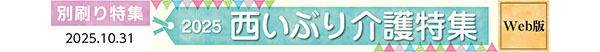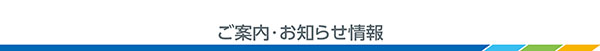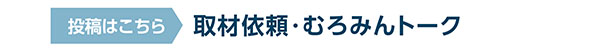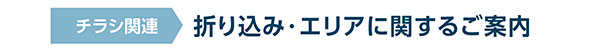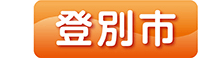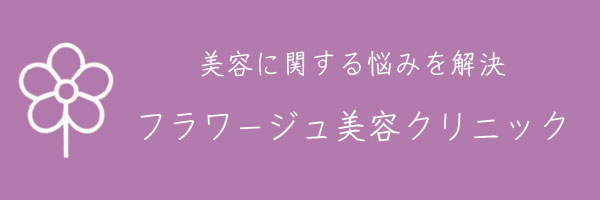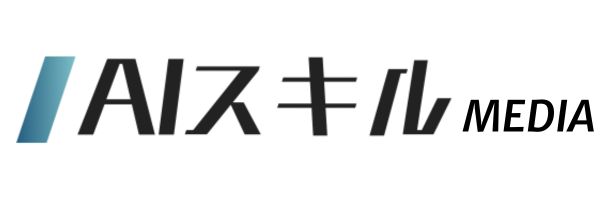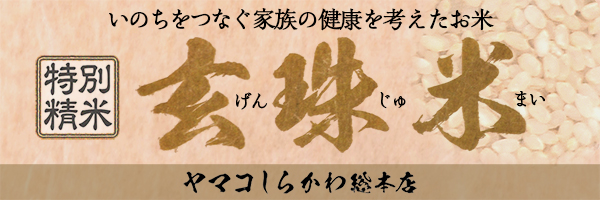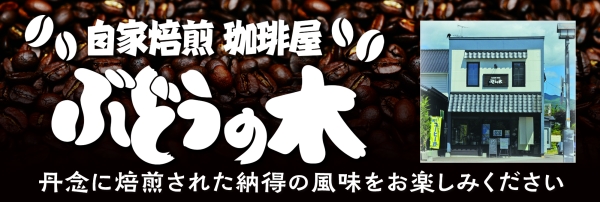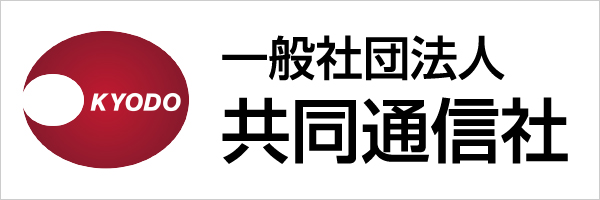武蔵野に住む作家・杉本隆治は、小説「野盗伝奇」を『甲信...
- トップ
- むろみんホットニュース一覧(電子版企画)
- はるみんオススメ書籍(19)「地方紙を買う女」
2025/07/14 11:30電子版企画
はるみんオススメ書籍(19)「地方紙を買う女」
ここから先の閲覧は有料です。
続きを読むには、ログインまたは新規会員登録(有料)をしてください。
電子版単独 月々1,800円(税込)
※紙面併読者は600円(税込)室蘭民報のニュース・イベント・お悔やみなど地域情報をWEBで閲覧できます。
電子版会員は全ての記事が閲覧可能となっております。
人口と世帯
2026年1月末 現在
室蘭市
73,061人(-140人)
42,490世帯(-67世帯)
登別市
42,659人(-68人)
23,641世帯(-35世帯)
伊達市
30,486人(-50人)
17,336世帯(+108世帯)
( )は前月比