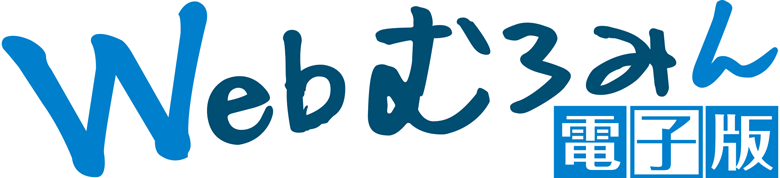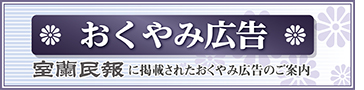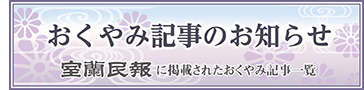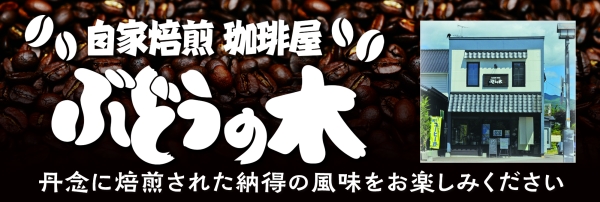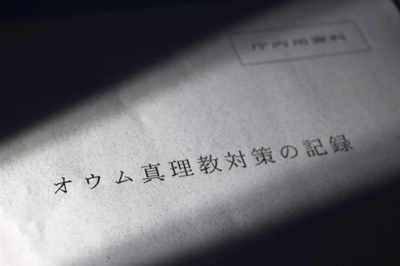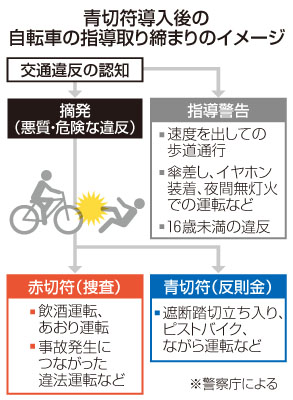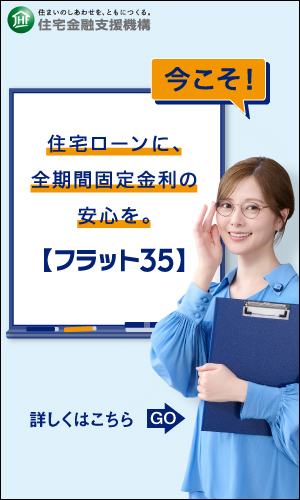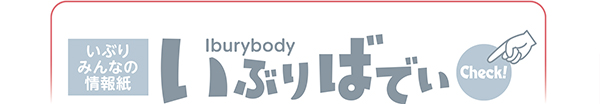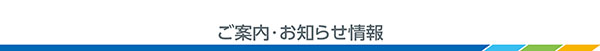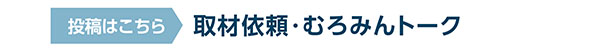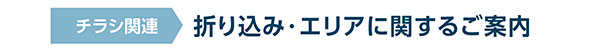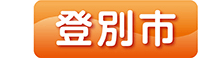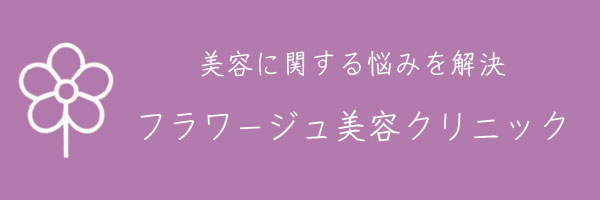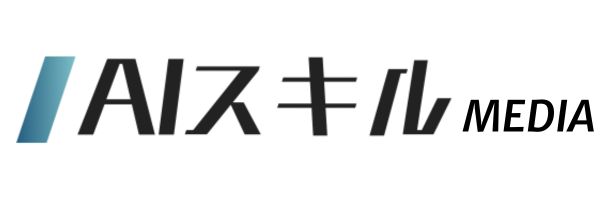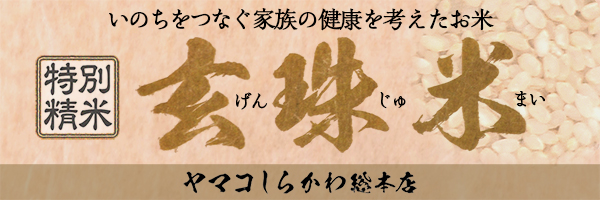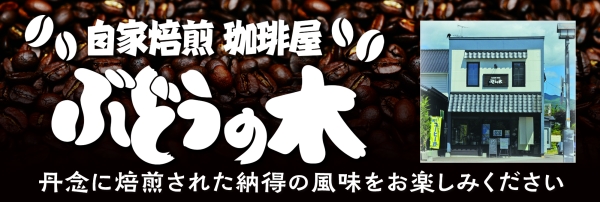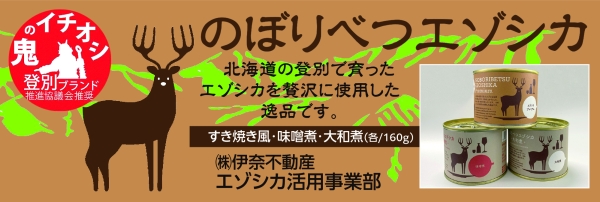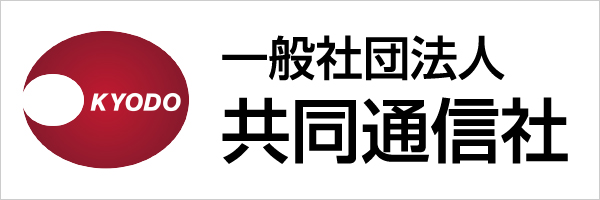「加冠の儀」で燕尾纓の冠をかぶられる秋篠宮家の長男悠仁さま=6日午前10時7分、宮殿・春秋の間(代表撮影)
秋篠宮家の長男悠仁さまの成年式が6日、執り行われ、悠仁さまは皇居・宮殿で中心儀式「加冠の儀」に臨まれた。男性皇族が成人した際、皇室の慣例で催す重要儀式で、1985年の秋篠宮さま以来40年ぶり。悠仁さまは昨年18歳で成人を迎えたが、大学受験のため、19歳の誕生日での開催となった。
6日朝、天皇陛下の使者が東京・元赤坂の秋篠宮邸を訪れ、悠仁さまは「冠を賜うの儀」で成年の冠を受け取った。
午前10時から皇居・宮殿「春秋の間」で加冠の儀を実施。悠仁さまは未成年用の古式装束と額当て「空頂黒幘」を着用して、いすに座り、侍従が額当てを外して、陛下から授かった燕尾纓の冠をかぶせた。天皇、皇后両陛下、秋篠宮ご夫妻ら皇族のほか、石破茂首相ら三権の長らが参列した。
悠仁さまは両陛下の前に進み出て謝意を伝え、主催した秋篠宮ご夫妻に「式を挙げていただき、誠にありがとうございます。成年皇族としての自覚を持ち、その務めを果たしてまいりたいと存じます」と述べた。
その後、悠仁さまは成年用の黒い装束に着替え、儀装馬車に乗って皇室の祖先らをまつる宮中三殿へ向かった。加冠を終えた報告として「賢所皇霊殿神殿に謁するの儀」で拝礼する。
午後は両陛下に感謝の言葉を伝える「朝見の儀」などがあり、大勲位菊花大綬章が授与される。
【成年式】男性皇族が成人した際、皇室の慣例で執り行う。古来行われてきた「元服」の儀礼に由来する。記録に残る確実な例は奈良時代の714年、聖武天皇が皇太子の立場で14歳で元服した例。天皇としての元服は平安時代の864年、清和天皇が初で、唐に倣って元服式が作成された。これ以降、江戸時代末まで続いた。明治時代に制定された皇室令(戦後に廃止)で正式に成年式と規定され、皇位継承資格者を内外に示す意義があった。現行法に成年式に関する規定はない。皇室典範に基づき、成年に達すると、摂政就任や皇室会議の議員選任への関与などの資格を得る。